コンシューマーズカフェ「食品表示の動向(衛生事項)」開かれる
2025年9月1日、第46回コンシューマーズカフェを開きました(味の素 協賛)。今回は消費者庁食品表示課 多田剛士課長補佐をお招きして「食品表示の動向(衛生事項)」のお話をいただきました。
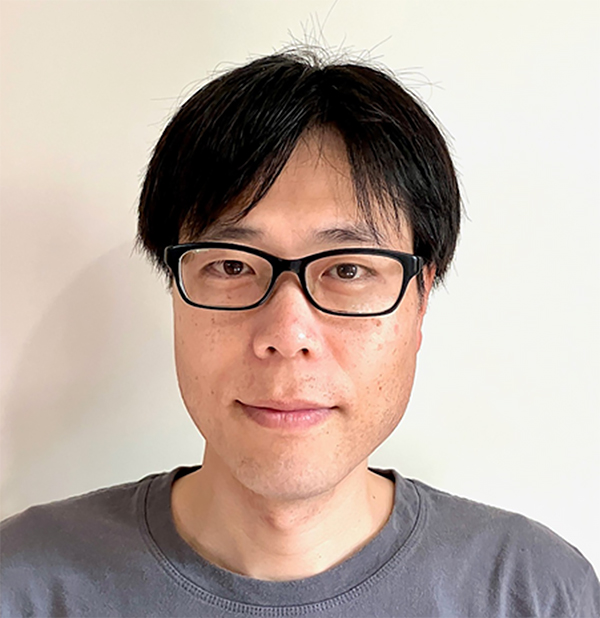
多田剛士さん
主なお話の内容
特定原材料等(アレルギー表示)について
食品表示法第4条に食品表示基準を定めなければならない旨が規定されており、この規定を受けて策定されている食品表示基準において、「特定原材料」を含む食品を販売する際にはアレルゲンについて表示しなくてはならない旨が規定されている。
「特定原材料」は現在8品目であり、この他、「特定原材料に準ずるもの」として次長通知で20品目を定めており、合わせて28品目を「特定原材料等」と言っている。
「特定原材料」の表示は義務であるが、「特定原材料に準ずるもの」の表示は推奨であり、義務ではない。
特定原材料等を追加する際には、3年ごと実施にする全国実態調査における症例数、重篤度の結果を踏まえて検討している。
食物アレルギー表示の変遷
食物アレルギー表示の制度は平成13年に創設されており、食品衛生法に基づく厚生労働省令にて規定された。
平成27年に食品表示法が施行され、アレルギー表示を含む食品衛生法にあった表示の規定についても食品表示法にまとめられた。
近年の動きとしては、令和5年3月にくるみが特定原材料を移行し、令和6年3月にマカダミアナッツを特定原材料に準ずるものに追加した。また、マツタケを削除した。
特定原材料に準ずるものの対象品目として追加する際の考慮事項:直近2回の全国実態調査の結果において、即時型症例数で上位20品目に入っているもの。もしくは、直近2回の全国実態調査の結果において、ショック症例数で上位10品目に入っており、重篤度等の観点から別途検討が必要なもの。
特定原材料に準ずるものの対象品目として削除する際の考慮事項:直近4回の全国実態調査の結果において、即時型症例数で上位20品目に入っていないもの、かつ、直近4回の全国実態調査の結果において、ショック症例数が極めて少数であること。
全国実態調査の結果
即時型症例数の推移を見るとカシューナッツは平成24年度で14位、令和3年度で7位であり、令和6年度も7位だが、全体に占める症例数の割合が上がっている。ピスタチオは令和3年度で20位、令和6年度で14位であった。
この結果を受け、カシューナッツは令和7度年中に特定原材料に移行させる方向。ただし、公定検査法を確立した段階で移行することになる。これと同じタイミングで、ピスタチオは、特定原材料に準ずるものへ追加する方向。ペカンナッツ、ヘーゼルナッツが今回20位以内に入ってきているので、次回の令和9年度の実態調査結果を踏まえて検討することになるだろう。
外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取り組みについて
外食・中食の食物アレルギー表示は、食品表示基準の対象ではないが、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針を踏まえ、外食事業者等が行う情報提供に資するよう、パンフレットや動画を作成し情報発信している。
栄養強化目的で使用した添加物の表示について
改正(令和7年4月)前までは、栄養強化の目的で使用される食品添加物(ビタミン類、ミネラル類等)には免除規定があり、表示することは任意であったが、この免除規定が廃止となった。
改正に当たっては消費者意向調査を実施しており、調査では、回答者の約半数が、栄養強化の目的で使用した添加物であっても表示してほしいと回答している。また、事業者への調査では、約1割が、栄養強化目的で使用した食品添加物の表示を省略した製品を扱っていると回答している。加えて、約9割5分の事業者が、栄養強化目的で使用した添加物について全て表示することになっても問題ないと回答した。
食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会について
令和5年にとりまとめられた「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージ」にて、平成17年に厚生労働省及び農林水産省が作成した「食品期限表示の設定のためのガイドライン」について、期限表示の設定根拠や安全係数の設定等の実態を調査し、有識者から構成される検討会を設け、食品ロス削減の観点から見直す、ということが示された。また、このほか、賞味期限が到来した食品で「まだ食べることができる食品」の取扱いについての具体的な検討も行い、食品寄附活動の促進につなげる、ということも示された。これを受け、検討会にて、食品ロス削減の観点の他、食品安全の観点も踏まえて議論を行った。
食品表示基準における、消費期限、賞味期限の定義は次のとおり。
消費期限:定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日
賞味期限:定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日
安全係数について、食品の特性等を踏まえて1に近づけること、としている。ただし、微生物が増殖する可能性が大きいと考えられる食品には、その特性等に応じて安全係数を設定する必要がある。
期限表示が導入された平成7年に厚生省(当時)及び農林水産省が通知した消費期限又は賞味期限を「5日」で区別する考え方は、用語の定義に基づく期限設定とはいえないことから、平成 20 年には解消されており、現在、消費者庁においても推奨していない。
改正のポイントは次のとおり。
①本来の用語の定義に基づき、食品の特性等を考慮しどちらかを正しく表示する。
②食品の特性等を勘案し、期限設定のための客観的な項目(指標)及び基準を科学的・合理的に自ら決定する。
③食品の特性等に応じ、安全係数は1に近づけること、差し引く時間や日数は0に近づけることが望ましい。一方、微生物が増殖する可能性等の大きい食品には、その特性に応じて設定する必要がある。
④商品アイテムが膨大であること等を考慮すると、個々の食品で試験・検査を行うことは現実的でないため、特性が類似している食品を参考にした期限の設定も可能である。
⑤消費者等から求められた場合には、賞味期限を過ぎてもまだ食べることができる期限の目安について、できる範囲で情報を提供するよう努める。
