日本食品安全協会 教育協議会講演会開かれる
2025年8月25日、日本食品安全協会 教育協議会講演会「健康食品のこれから」がハイブリッド形式で開かれました。会場(関西大学東京センター)とあわせて約250名の参加がありました。初めに北市 清幸 理事長より、今回は多様な立場の講師に参加いただいて、今、注目されている機能性表示食品制度に関する講演会を開催するという趣旨説明が行われました。
「機能性食品制度見直しのポイント」
消費者庁食品表示課 保健表示室課長補佐 鮫島 那奈さん
機能性表示食品の制度の見直し内容について話された。
健康被害情報の収集体制
改正後、機能性表示食品に係る健康被害情報は、医療機関からでなく届出者からも消費者庁や知事への報告が義務化された。因果関係が明らかでなくても、健康被害の恐れがある場合は報告する必要がある。
適正製造規範(GMP)遵守の義務化
サプリメントの原材料受け入れから中間品や製品を製造し、製品を直接触れない状態に包装して出荷するまでの工程を行う製造施設がGMPの義務化対象となる。これまでも製造はHACCPに基づいているが、GMPによる管理も求められる。原材料を受け入れる時に品質を確認し、文書化された手順で製造・記録する。これらを踏まえて、製品の出荷可否を判断することが求められる。原材料の製造施設においてもGMP管理が行われることが望ましい。消費者庁は届出製造所におけるGMP実施状況の確認と助言を、経過措置期間である2026年8月末までの間に行う。
容器包装の表示見直し
商品の情報をわかりやすくする。改正後、枠で囲んだ「機能性表示食品」という文字と届出番号を表面の上部に書くことになった。製品による臨床試験を行っていない届出の場合は、機能性関与成分について報告された機能であることを的確に表示する必要がある。複数成分を含むときも、各成分とその機能の対応がわかるようになる。
改正後の届出に関する事項
届出マニュアルを廃止して、「機能性表示食品の届出等に関する手引き」を作成した。告示と通知で定められた事項があるので、それぞれ字体を変えて、区別して示してある。
慎重な届出確認が必要なケースで、確認期間の見直しを行った。消費者庁は、届出された日から60営業日以内で確認するが、慎重な確認が必要と考えられるケースでは120営業日以内とし、専門家の意見を聴く。この対象となる場合は届出者にお知らせする。
1年ごとに自己点検と評価の報告をしてもらう。報告しないと機能性表示食品としての要件を欠くことになる。届出の内容は、届出データベースで公開されている。
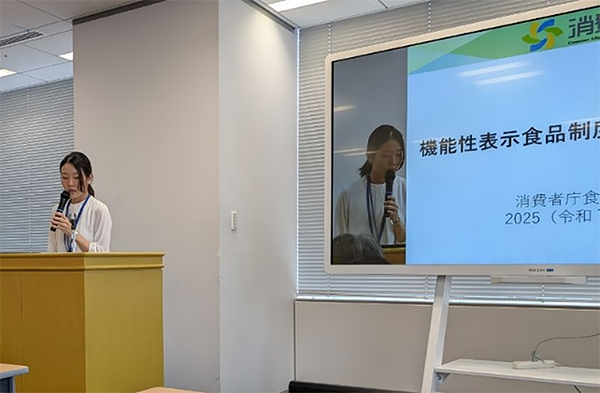
鮫島那奈さん

今川正紀さん
「食品安全行政の動向~いわゆる「健康食品」のこれまでとこれから~」
厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課長 今川 正紀さん
小林製薬の紅麹を使用した機能性表示食品をめぐって
いわゆる健康食品は保健機能食品(食品表示法によって定められる栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品)と「その他のいわゆる健康食品」に分けられる。
2024年3月、小林製薬の紅麹を使った食品のうち3製品に回収命令が出た。5月末、健康被害が報告された食品にはプベルル酸が含まれていること、工場内のアオカビがプベルル酸を作るらしいこと、紅麹と共培養されて化合物YとZを作ることがわかり、動物実験が始まった。
日本腎臓学会の調査により、摂取開始時期、摂取期間の長短に関係なく、2023年12月から3月に健康被害が集中し、腎臓の尿細管に障害が生じることがわかった。
医薬品食品衛生研究所では、令和5年6、7、8月に製造したロットに原因があることを突き止め、腎毒性の検証を行った。アオカビがコメ培地を栄養源としてプベルル酸ができる。化合物YとZの構造式が判明し、アオカビと紅麹の共培養で生成されることがわかった。
食品衛生法上の措置や規格基準作成、施行規則作成が必要かどうかは今も検討中。
今後の対応
これらを踏まえ、機能性表示食品などに係る健康被害の情報提供が義務化された。
背景として、小林製薬が内部で一定の結論が出てから報告したので消費者庁・大阪市へ報告までに2か月かかった。これは被害拡大につながる恐れがある。
事業者における対応
食品全般については、これまでと同じように健康被害と疑われる情報を把握したら知事等への情報提供を努力義務とし、健康被害関連情報の収集を行い、健康被害の発生・拡大の恐れがあるときは速やかに知事等に報告することが求められるが、機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)については、努力義務ではなく義務として、健康被害と疑われる情報を把握した時点で知事等への情報提供が必要となる。つまり、健康被害に関する情報収集と情報提供が義務となり、その食品に係る衛生管理計画の作成・遵守が義務となった(2024年9月施行)。収集された情報は公表していく。仮に個々の事例で食品衛生法上の措置の必要がないと判断した場合も、事例が積み重なったら、再度議論する場合もあるだろう。
重ねて言うと、営業者は、努力義務に加えて、トクホと機能性表示食品に関する健康被害情報は自治体に速やかに報告すること。重篤な時は15日以内、重篤でなくても30日間に2例以上発生したら15日以内に報告する。
情報提供の義務が課せられるのは、トクホと機能性の届出者、トクホの許可者。サプリメントも衛生管理計画をつくる義務ができた。事業者用、保健所用、厚労省報告用の3書式が統一されて報告がしやすくなった。医師が「因果関係が否定できない」としているものも記入して提出する。被害が拡大する恐れがあれば速やかに届ける。
保健所の情報は厚労省に集められ、月1回開催される小委員会でまとめる。
食品との関連が否定できるときは食品衛生法上の措置はない。情報不足のときは、継続して情報を収集する。食品健康被害情報管理室(省令室)を設置し(格上げ)、食品監視体制を強化した。
「健康食品の安全性確保に対する取り組み」
一社)健康食品産業協議会 理事 櫻井 護さん
健康食品産業協議会(JAOHFA)とは
私たちの理念は、健康食品が人々から高く信頼されるように、健康リテラシー向上と産業の健全な育成・振興。2009年に健康食品の業界団体5団体が集まってできた。会員は増加中で、信頼される健康食品を目指す機運の高まりの現れだと思っている。
健康食品の安全性確保に関する行政からの提言とその背景
これまでの被害事例のほとんどは医薬品成分が含まれたケース。
1990年(米国)トリプトファン製品中に不純物混入 健康被害あり
1996年(台湾)、2003年(日本)アマメシバの過剰摂取により被害が生じた
1998年(日本)、1993年(ベルギー)アリストロキア属植物による健康被害
1978年(米国)コンフリーに含まれる有害なアルカロイドによる健康被害について厚労省から注意喚起
2003年(日本)中国茶「雪茶」の利用法による健康被害
被害には経済被害と健康被害がある。これらは製品に問題があるわけだが、過剰摂取や病人の摂取など利用法に問題があることもある。適正に製品を作り、適正に利用する!
2008年に厚労省の通知があった。「製造段階」における原材料安全性やGMPによる安全性確保、積極的な健康被害情報収集、消費者に対する普及啓発では適切な摂取量目安の表示と注意喚起を行う。
市場は微増していたが、小林製薬の件で市場は縮小。健康被害報告の遅れ、品質管理の失敗、新規成分での機能性表示、消費者が医薬品と誤認するなど、2008年に提言・指摘されていたことが起こってしまった。
JAHFAの取組み
事業者のアンケート(2025年実施)を行ったところ、小林製薬の影響が大きかったことがわかった。問題は情報収集と報告にある。これらは努力義務から報告義務となった。患者の個人情報を医者なら知らせていいか?医者からの情報収集がうまくいくか?など、企業は報告の判断基準が不明で不安を感じている。
製造段階、原材料の安全性確保、利用者の体調変化やその対応について、チェックリストを作った。歴史を含めて、事業者への啓発教育も重要。
個別事業の取組み~サントリーウエルネスでは
事業者は、科学的根拠によって安全性・有効性が確保され、その根拠が国際的に容認されている原材料を用いて、GMPに基づき製造した製品を安定供給する。ことに海外原料にも徹底した品質管理を行っている。
残された課題
2024年のサプリメントによる重篤な健康被害では、予期せぬ成分が混入してしまい、最初の症例把握から消費者庁への報告まで二か月かかってしまった。原材料の品質を保証できる仕組み、適正な広告と売り方が重要。HACCP、GMPも導入して実現していく。

櫻井 護さん
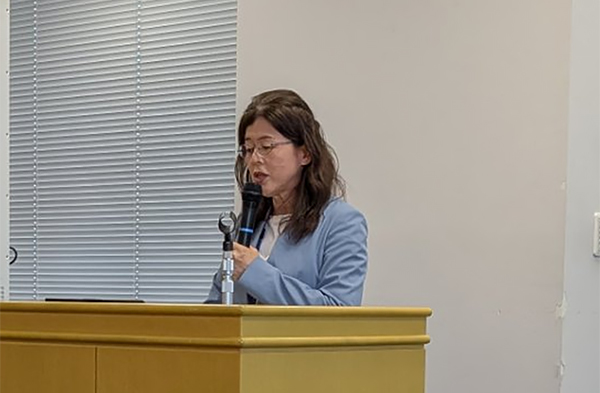
森田満樹さん
「消費者から見た健康食品」
一社)Food Communication Compass 代表 森田 満樹さん
健康食品を取り巻く状況
サプリメントの摂取状況(国民健康・栄養調査結果 2019年)を見ると3~4割の人が使っていることがわかる。消費者がほしいものが販売されるので、消費者教育が重要だと再認識する。サプリメントというとシニアの健康維持・増進ばかりかと思うが、若い男性のプロテイン、若い女性のビタミンはよく利用されている。
消費者委員会では健康食品への関心が高く、健康食品を使ったことがない人は25%しかいないことに注目している。
利用目的では、病状改善を求めている人が利用していることが問題。食品の食べすぎではありえないような「過剰摂取」が、錠剤だと起きてしまう。
東京都医師会では「サプリメントや健康食品で健康を損ねていませんか?」という冊子を出している。健康食品は自己責任で、客観的モニタリングができない。医薬品との併用や過剰摂取のリスクがある。
PIO-NETという全国消費生活情報ネットワークシステムの調査よると危害情報の1、2位に健康食品があがっている。指定成分等含有食品制度があって注意喚起が行われていても、被害が出続けている。指定成分等含有食品の意味を知らない人が多い。
健康食品と薬の相互作用にも気を付けてほしい。
保健機能食品の種類と特徴
健康被害はあるが、消費者は健康食品を求めているのだから、自ら表示をよく見て、できればデータベースも見てほしい。
2015年から機能性表示性食品制度がスタートした。保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品があり、トクホ以外には生鮮食品もある。
トクホは疾病リスク低減表示ができてマークがついている。現在、品数は減っている。栄養機能食品にはアメリカからきているサプリが含まれる。届出が不要なので市場規模はわからない。食事摂取基準が改正され、栄養機能食品の表示の検討が秋から始まる。
機能性表示食品の届出情報は消費者庁のWEBサイトで見られる。今回の見直しで機能性表示食品であることと番号が製品表面の右上に四角で囲んで書かれるようになる。医薬品との相互作用を書いてあるものもある。
食事のバランスが基本であることは保健機能食品にはすべて書かれている。
健康食品の課題
紅麹関連食品をめぐって調査されて分かったこと、今後の取り組みについては消費者庁のWEBサイトに公開されている。消費者委員会の意見書の中で消費者保護の取り組みの重要性も述べられている。食品安全委員会などのよい啓発サイトもあるが、認知度は低いのが課題。
