食のリスクコミュニケーション・フォーラム「培養肉のリスクとベネフィット」
食のリスクコミュニケーション・フォーラム2025第2回「培養肉のリスクとベネフィット」が2025年6月21日に開かれました(於 東京大学農学部フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール)。培養肉の安全性の考え方、消費者の受け止め方、国内外の消費者意識調査などについて、3名の講演がありました。
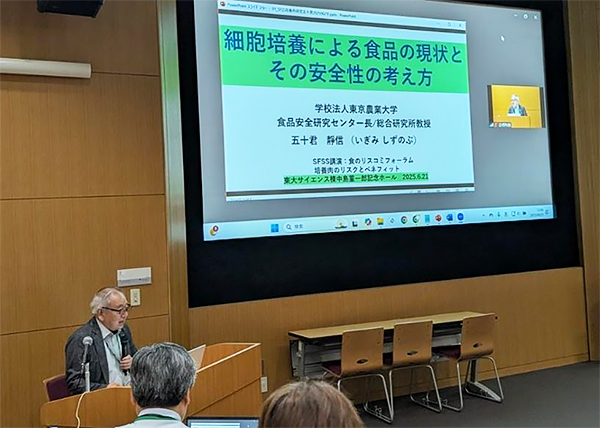
五十君静信さん
1.「細胞培養による食品の現状とその安全性の考え方」
東京農業大学食品安全研究センター長 五十君 静信さん
(1)細胞培養食品の現状と安全性の考え方
タンパク危機対策として国内外で代替プロテイン研究が進められている。シンガポールは世界で一番早く細胞培養食品を認可してランチ価格で培養した鶏肉が提供されている。海外で許可されている動物の種類としては、鳥類の肉を扱っているところが多い。
私は「食の最大のリスク」は食料が供給できなくなることだと考えているので、タンパク危機は最大のリスクと言えるだろう。食品そのものの安全は、長く安全に利用してきた歴史とどのように食してきたかの経験(食経験)に基づいて判断される。したがって食経験のないものの安全性は検討される必要がある。安心は個別対応になるが新規食品では特に配慮が必要。
(2)リスク評価に関する研究班紹介
令和4~5年、食品安全委員会「細胞培養技術を用いて製造される食品のリスク評価手法に関する研究」が行われた。具体的には、海外の情報収集とモデル細胞培養肉を作って(女子医大 清水先生 他)安全性に関わる検討を行った。鶏由来の細胞を大量培養して回収し、網羅的解析による評価を行った。鶏の線維芽細胞では培養する際に安全性の懸念される足場や血清が不要である。
海外の安全性評価のための情報収集からリスク評価項目の抽出を行った。モデル培養肉の検討では、食経験のある鶏肉を比較対照として良いかという課題について、網羅的解析(栄養、遺伝子、タンパク質、代謝産物)を行い考察した。
(3)海外の安全性に関する動向と情報の整理
シンガポール食品庁(SFA)、米国FDA、FAO、欧州EFSA、FSANS、英国食品基準庁、カナダ等の情報を調査した。調査の結果、危害要因と想定されていたのは、「最終プロダクトに含まれていて食経験がないもの」、「足場(今は、マイクロプラスチックに替わる足場材を探しているところ)」、「凍結保護剤」、「材料や機器からの汚染(ウイルス、細菌)」、「成長因子」、「動物血清の使用の有無」、「培地成分に含まれる食習慣のない材料」など。
海外では「細胞のアイデンティティ」を求める。アイデンティティとは細胞の由来、どのような細胞なのか、細胞の起源、遺伝子操作が行われているか、増殖中に細胞が変化しないかなど。腫瘍形成能と不死化、意図しない毒性物質産生やアレルゲン、栄養成分の情報も必要。
シンガポール食品庁:SFAは2023年1月に世界初の商用販売の認可を出した。食糧自給率10%を培養肉で30%にしたいという。培養うなぎ、培養魚肉、脂肪細胞を作ろうと、高い期待感を持つスタートアップ企業が多い。世界初に名乗りをあげ、ガイドラインはすでに20数回リバイスし、改善していく方向のようだ。
オーストラリア:Vow社は日本ウズラの培養肉を作製。今後は、カンガルー、アルパカ、カメ、シマウマ、水牛など珍しいものを取り上げる。シンガポールと対照的なのは、厳密なデータをとっていたこと。
アメリカ:FDAとUSDAによる2段階の規制体。FDAでは、細胞収集、細胞バンク、増殖分化プロセスをみる。USDAで、細胞収穫後の処理、包装、表示をみる。ガイドラインはないが、生産プロセス、セルバンク、脂溶成分などの安全性データを提出し、FDAの専門家の安全性に関する質問に答えられたら合格でそのやり取りをwebに公開。登録は施設ごとに行い、GMPで規制している。州ごとに対応は異なる。フロリダ、アラバマは禁止。
EU:東京農大でEFSA専門家とのワークショップを行った。まず新規食品の安全性ガイドラインに従い、次に培養肉に特化したガイドラインに従う必要がある。海外では食経験の定義ができていて、該当しないと新規食品として申請する。日本には新規食品の定義がない。欧州のガイドラインでは細胞のアイデンティティが求められる。
イスラエル:培養肉のビーフステーキがイスラエル保健省より承認された。
先進国は培養肉を重要なタンパク源と見ており、2024年度末、培養肉のガイドラインや審査が進められているのは、10か国(USA、EU、UK、イスラエル、シンガポール、スイス、タイ、韓国、オーストラリア・ニュージーランド)。日本では民間で培養肉の研究開発が行われているが国の細胞培養肉のガイドラインはできていない。消費者庁でリスク管理のガイドラインが策定される方向で、検討が進められている。欧州では培養肉の安全性を新規食品の一部として評価しているが、日本にも新規食品の枠組みが必要なのではないか。
(4)実際に細胞培養を行った研究内容の紹介
鶏卵胚の鶏モモ肉の細胞を培養し、細胞変化を見ている。カルチャープレートに付着する細胞と着かないものがある。それぞれを継代して各世代の細胞の解析を行った。増殖率がいい細胞を探す。商業生産には不死化技術が必要になるだろう。
現在まで、細胞間の遺伝子発現の違いはあまり認められない。プロテオーム解析を見ると、市販の鶏モモが多様な細胞の集合体であるため比較基準とするのは難しい。栄養成分においては(乾燥させた鶏モモと培養肉の粉末を比較)ビタミン以外はあまり変わりなかった。
2.「培養肉は人々にどう受け止められるのか:意識の国際調査の紹介」
弘前大学人文社会科学部 教授 日比野 愛子さん
(1)培養肉に対する人々の理解
社会心理学は個人の心理より社会にあるグループの特徴、マクロな変化を解明するもの。欧州では、新規技術へのパブリックアンダースタンディング(公衆の科学理解)への関心が高い。科学は未知なるものを生み出すが、これがファミリアになっていくプロセスをみていく。
1990~2000年、遺伝子組換えやクローン技術が世に出たころに欧州では大規模な社会心理学の研究をしていた。未知なるものが登場すると、メディア報道や「らしい」表象の出現が急に増えてやがて落ちた。
培養肉は27か国以上で市民意識調査が行われている。それを見ると、認知度が上がり、食リスク認知の感じやすさは下がり、不自然さの認知が下がるにつれて受容性が高くなる。日本の調査では「食べたいか」に対しては、食べる、どちらでもない、食べないが3等分だった。食料危機の改善、動物福祉改善には賛同がみられた。国内外を比較して、「どちらともいえない」が多いのは日本の特徴。日本人は新食品に抵抗しやすいのか。日本人の「わからない」の分析が必要ではないかと考えている。ゲノム編集の場合の「わからない」には個人では判断できない、今は未だ判断できないなども含まれる。
培養肉の受容性を左右するのは何か。不自然さの認知(培養肉は不自然だから食べない)が効いている。食糧危機に貢献すると思うと、食べたいと思う人は増えるだろう。生命観(地域や文化の生命観)も影響する。細胞を生命だと認識する人ほど食べたいという人は増える。また自然だと思うと食べたい人と食べたくない人の両方が増える。アンケートでは、「自然」「不自然」の問い方は慎重であるべき。大まかに生命観、認知度、環境問題への関心、不自然さの認知、年齢が日本での規定因子と考えられる。
中国は健康的なものを受容する。インドは倫理的であることを受容する。
では、安全性は受容性に影響するのか。「値段が高くて栄養がある培養肉」、「既存食品程度の栄養があり安い培養肉」などの様々なケースを提示し、肉種別(培養か、昆虫か、従来の肉か)、価格、栄養価、安全性の受容を見ると、安くても昆虫は人気がなかった。
培養肉に影響するのは「不自然さ」で、不自然さへの倫理的説明が必要になりそう。日本の特徴の「どちらでもない」という意見不表明をよく見るべき。
(2)日本の人々の反応:意識の国際調査より
日本、シンガポール、デンマーク、イタリア、オーストラリアで調査を実施。
促進の政策上のドライビングフォースとしては、食糧危機、経済的展望、環境配慮が挙げられ、抑圧するドライビングフォースとしては食文化保護、畜産保護が挙げられている。
シンガポールやイタリアは食べてみたい人が多く、デンマークは食べてみたくない人が多い。
シンガポールは認知度も高く、温暖化軽減が評価されている。イタリアは認知度が高く環境貢献の認知も高い。回答者の主たる情報源はテレビやSNSだった。SNSが今後よいサイエンスコミュニケーションのモデルになるといいのだが。
自国の食文化に誇りをもっているからといって食べてみたくないわけではない。食料問題への貢献、食文化の尊重、安全性確保ができれば、培養肉の受容は上がるだろう。不自然さの認知の影響は国内外とも大きい。産官学を信頼している人は食べたくなる。
政策において培養肉推進のシンガポール、消極的なイタリア。それぞれに世論では培養肉に肯定的。日本はこれにあてはまらない。培養肉の不自然さの認知が強い。腑に落ちる理解が必要だろう。
(3)情報提示とその反応 研究中の中間報告
社会的意義を前面に出すと認知はアップする。既存の肉と同じというと変わらず、高度技術であると示すとダウン。これは新規の食べ物の認知ではよく見られる傾向。技術情報のジレンマであり、技術の透明性は求められるが、技術情報を提供しても態度の好転に反映されにくい、と木下富雄先生も言われている。一方、周辺情報を示しても技術の説明がないと信頼は下がる。人々の懸念を意識した情報公開が必要。全部が培養肉に置き換わるわけでないことも消費者に伝えることは重要。以下のような情報提供が重要。
- 食料危機解決の可能性がある
- 環境負荷軽減に貢献する
- 安全性が認証されている
- 製品の販売がすでに始まっている
- 既存の畜産業への影響は限定的
リスクコミュニケーションに関わる者としては技術の説明やリスクに関する情報は無力ではないはずだと思いたい。
(4)培養肉のコミュニケーションに向けて
「培養肉」という名称でよいのか。対話のプロセスや多様な表象を通じて馴致の可能性もあるだろう。SNS時代のコミュニケーションの可能性と課題を見ていかなくてはならない。その中でリスクの基本情報を伝えることも重要。
今後、不自然さの影響の強さ、「わからない」回答が多い日本人の食料供給への意識、背景やロードマップの説明によって不自然さを和らげる効果など、検討課題だと思う。
「Cultivatedという選択:新規食品の用語をめぐる国際的合意と消費者理解」
GFIジャパン マネージングディレクター 洪(ほん)貴美子さん
はじめに
GFI(Good Food
Institute)は、2016年に米国で設立され世界7拠点で活動している、寄付によって成り立つ非営利団体(職員230名)。寄付の7割超が個人寄付で、アメリカはじめ世界富裕層が多い。日本拠点は2024年秋に設立。
世界人口100億人をどう養うのか?人獣共通感染症拡大の中で、持続可能性、効率性、安全性を考えると培養肉も有力な選択肢のひとつ。バイオ研究は開発期間が長く、中小企業には手が出ないので、研究開発には国の長期的な支援が必要。ことにアジアの人口増加は顕著。日本人口は減少しているが、中国、インド、インドネシア、韓国は動物性タンパク質需要が増加。食は私的なもので強制できないが、原料提供の蛋白源(植物性、微生物由来、動物細胞由来)の多様化を考えるべき。食肉生産効率でみると、牛、豚、鶏の順で飼料の変換効率は高くなる。培養肉に対する不自然さによる心理的障壁を、味も価格も同等またはより良くすることで解消できるのではないかと考えている。
用語の問題
cultivatedという言葉についてGFIではずっと調査してきている。
2019年、cultivateが良く、購買意欲も上げることがわかった。「Cultivated」「cultured」「Cell
based」を比べるとcellとculturedはネガティブ。
名称選びの3大論点は「消費者の安心感(行動を起させる言葉であること)」、「一貫性(表示制度との整合性があって、既存食品との差別化できているか)」、「国際協調」。日本での言葉選びでは英語に翻訳されたときの影響力にも注意が必要。
同年、アメリカ意識調査で認知度が高かったのは「Lab grown meat」で、好感度が高かったのは「Cultivated」だった。アメリカでは認知度の高い「Lab
grown」は6割拒否だった。
2023年に向けてcultivateの認知が上がり、2024年度には購買動機は、好奇心、環境配慮、と殺不要、健康への配慮のいずれも3割程度だった。試食で期待が上昇したというレポートもある。44~45%が、培養肉は従来の肉と同等かそれ以上と栄養面での期待が持たれていた(高タンパク、飽和脂肪酸が低い、コレステロールが低い)。
技術説明は消費者の行動変容の促進になっていないことが欧米の調査でわかっている。
中国では国家戦略の3本柱(食の安全、農業の高度化、未来食品産業)中で、細胞農業も国家戦略のひとつ。細胞株確保、培養機器開発、規制の枠組み作りが行われており、用語は「細胞培養肉」が政府と学術会で使用されている。
国内外を通じて名称決定は重要な戦略設計プロセスと見られている。
ハラル認証について
世界人口の24%
がイスラム教徒。培養肉のハラル認証について東南アジア、中東諸国で検討が始まっている。ハラル原則に従い、と殺して放血するときにコーランを唱るなどしてタネ細胞を採取すればいいことになった。バイオプシーでの細胞採取された非と殺由来細胞は協議中。培養肉バリューチェーンとなるためにシンガポールに隣接するマレーシアは量産技術のフィージビリティ研究を始めた。
タイでは代替タンパク質バリューチェーン未来戦略共創として、研究開発、人材育成、国内インフラを行っている。
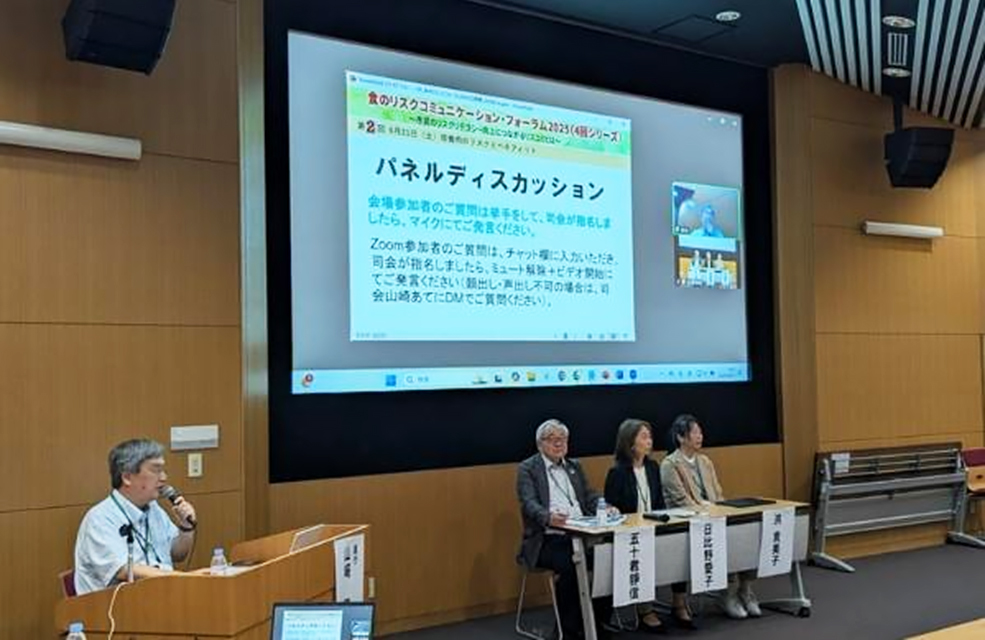
会場参加者とオンライン参加者からの質問を受けて、NPO法人食の安全と安心を科学する会 理事長 山崎 毅さんの司会のもと、質疑応答が行われました。
