「作物の育種は突然変異の探索と利用の繰り返し」
2025年5月28日、TTCバイオカフェを開きました。お話は東洋大学食環境科学部食環境科学科 准教授 津田麻衣さんによる「作物の育種は突然変異の探索と利用の繰り返し」でした。このバイオカフェは国際植物の日にちなんで企画いたしました。
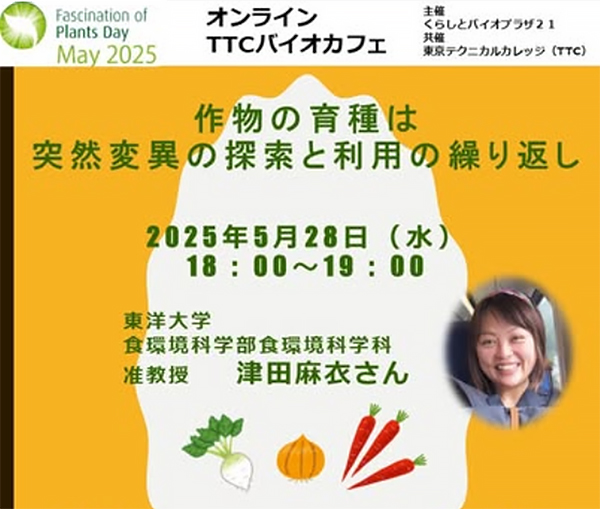
案内チラシ
主なお話の内容
自己紹介
福井県出身。高校の時、看護か農学かのいずれかを進路とする友人が多い中、植物が好きだったので農学部に進み、育種に関わるようになり今日に至る。今日は自分の研究というより、「育種(品種改良)」とは何か、研究現場の苦労についてお伝えしたい。
イネ「コシヒカリ」
長い間、人気の高いコシヒカリが誕生したのは1956年。農林1号と農林2号をかけ合わせて作られた。1号と2号の孫世代、3000個体から65株が選ばれ、うち20株が福井県で栽培された。1953年、福井県でコシヒカリが生まれた。その後、全国での試験栽培を経て農林100号と名付けられた。千葉県と新潟県は奨励品種に指定した。初めの交配から12年かかっている。コシヒカリからは、秋田こまち、ひとめぼれなど人気の品種が生まれている。
りんご「ふじ」
りんごといえば、「ふじ」が有名で、世界一の品種になったこともある。味、貯蔵性、甘さが優れている。交配から誕生まで23年かかった。果樹はイネのように毎年1世代というわけにはいかず、育種に時間がかかる。岩手県には「ふじ」の原木が今も残っている。
「ふじ」と名付けられ理由は、育成地が青森県の藤崎町であった、富士山にちなんだ、栽培者が女優の山本富士子さんのファンだったなどといわれている。
ぶどう「シャインマスカット」
今、人気のシャインマスカットは皮ごと食べられて、甘い種なしブドウ。種なしはジベレリンという植物ホルモン処理によるもので、品種によるものではない。シャインマスカットはアメリカブドウ品種群(寒さに強い)とヨーロッパブドウ品種群(皮が薄くて甘い)の雑種。48年かかって開発された。
トマト「桃太郎」
よく知られている「桃太郎」はタキイ種苗が開発した。高度経済期の日本では、都市近郊でトマト栽培ができなくなり、完熟してから輸送することが難しくなった。それまでのトマトでは長期輸送に耐えられなかった。青いトマトを収穫し、店頭で赤くしたがおいしくなかった。
実を固くして輸送に耐えるトマトを作ろう。当時は赤すぎると敬遠されていたのでピンク色にすることを目標に交配を続け、1日100種以上のトマトの食味試験をし、13年かかって桃太郎が誕生した。
その他
ナスの野生種は黄色がかった緑色だったが、人が使ううちにアントシアニンの遺伝子に突然変異が入って黒に近い紫になった。
大豆の原種はツルマメで小さくて黒い。これが栽培化されて大きいダイズになった。
突然変異と栽培化
生物が生きるための情報はDNAに書かれており、その並び方で情報を示されている。生物は自分と同じ配列のDNAを複製しながら生きている。正常に複製されると同じ配列になるが、紫外線、細胞分裂時のミスなどで複製ミスが起きることがある。これらのDNA配列の変化を突然変異または変異という。
変異には次のようないくつかのタイプがある。
挿入:初めになかった1塩基または配列が入る
欠失:塩基や配列がなくなる
逆位:並んでいた塩基が入れ替わる
重複:同じ配列が重なって入る
1塩基多型:1塩基が入れ替わる
栽培中にどのくらい変異が起こるのか。普通に栽培しても、実った米のDNAと初めにまいた種のDNAでは41か所の変異が入っていた。イネには4億3千万の塩基があるが、1世代で41か所くらいずつの変異が特別に手を加えなくても入る。普通に栽培していても変異は入るものだが、変な性質が入った種を除いていくので、品種は維持される。一方、栽培種は変異が蓄積されて生まれたといえる。
野生種に突然変異が蓄積し、ヒトに都合のよい品種を選びとっていくことを「栽培化」という。何千・何万年の中で栽培化がなされてきた。
原種と作物
トウモロコシ:トウモロコシの先祖は7000年前のテオシント。実の数が少なく、小さい。人が選抜、育種をして、食べやすく、使いやすい今のトウモロコシを得た。
オオムギ:原種は粒が小さく、落ちやすかったが、今は実が大きくて、落ちないので収穫しやすくなった。
コムギ:エジプトの5000年前の遺跡にコムギ収穫の壁画がある。動物を使って刈り取りをしている。現在の栽培小麦はこのコムギの雑種からできた品種らしい。
イネ:今のイネは「オリヴァ・サティヴァ」。中にはインディカ米、ジャパニカ米などがある。突然変異の集積により倒れにくく、実が落ちにくく、収量が増えた。
枝がわり
私たちは突然変異を目にすることもある。よい例はハナモモ。薄いピンクの花をつける木に濃い紅色や白い花がつく。枝がわりと呼ばれるが、これは花の遺伝子に突然変異が起こっている。 りんごのフジの枝がわりで黄色いリンゴがなったこともある。これは果皮の色の遺伝子に変異が生じている。枝替わりの枝を挿し木で増やすと、黄色のフジを生産することもできる。濃い赤い縞が入る「みしまふじ」は秋田県で発見された枝がわりとして有名。
コムギ「農林10号」
コムギ「農林10号」は10年かかって作られた。草丈が低く、実がたくさんできる。このコムギを開発したのが稲塚権次郎さんで、「ノーリン・テン」という映画にもなっている。茎が短くて機械収穫に向いているが、病害に弱く日本全国には普及しなかったが、「みどりの革命」に貢献した品種として有名。
1945~60年、化学肥料を使いコムギの大量増産が実現し、数億人の飢餓を救った。このコムギ品種の親になったのが農林10号。これを達成したのはノーマン・ボーローグで、彼は農学者だが、飢餓への貢献からノーベル平和賞を受賞している。
ミラクルライス IR8
草丈が高いと倒れやすく、収量が減る。そこで倒れないが収量が低いイネと倒れるが収量が高いイネをかけあわせてIR8が誕生。1960年代、IR8ができて収量が上がった。フィリピンのデータを見ると栽培面積は微増なのに、生産量が大きく増えている。
遺伝資源があるときの育種の流れ
どんな作物をつくりたいか「目標」を決めて、それに合う遺伝資源を探す。
ジーンバンクには国内外の品種、野生系統の種子が保存されている。
たとえばイチゴでは、除雄といって、雄しべを取り除いた花にかけたい相手の花粉をつけて雑種をつくり、種をまく。すると雑種が1万株くらいできて、選抜していく。
ダイズは花が7ミリほどで小さい。咲く前の花を開いて除雄し、めしべにかけたい相手の花粉をつけ、タグをつける。
イネは放っておくと自家受粉してしまうのでお湯に漬けて花粉を殺し、かけたい花粉をかけて袋をかける。1個体から数十から百個の子ども生まれる。通常親Aと親Bから子どもが数十から百数十個体、孫は数百から数千個体得られ、このうちの50個体を展開する。たとえば「銀河のしずく」は51集団・9000個体から得られた31系統から耐病性、耐冷性などを調べて7年間の試験を経て生き残った1系統。
遺伝子資源がないときの育種の流れ
1900年ごろから交配による育種が始まった。「自然が起こした変異の中から、人間は自分たちにとって有用な方向で改良を進める。こうして人間は役に立つ品種を作り出していく」とチャールズ・ダーウィンは言っており、これは1859年のこと。育種が本格化するよりもずっと前。
遺伝資源がないときは突然変異を誘発する。その方法は交配育種、培養育種、薬剤やイオンビームによる突然変異の誘発などがある。これらにより短期間で突然変異を得られる。
培養するだけで変異が入る。ゆめぴりかは組織培養で作られ、もちもちしておいしい。
ミルキークイーンはメチルニトロという薬剤で誘発された突然変異を利用した。レイメイは放射線によって変異が入り倒れにくくなった。望まない変異も生まれるが、都合がよいものだけを選抜する。
ゲノム編集技術では、クリスパーキャス9を使って植物が持っている遺伝子の狙った場所を切る。修復が起きる段階で変異が入ることがある。これまではランダムに変異を入れて望まない個体を除外したが、ゲノム編集は遺伝子を狙って変異を入れられる利点がある。遺伝子組換え技術はその生物の持たない遺伝子を入れることができる。ゲノム編集も遺伝子組換えでも、安全性を様々な面から確認したものが、作物になっている。
ゲノム編集では外来遺伝子を最終的には除外している。
