サイエンスカフェみたか「アメリカザリガニから地球環境へ」
2025年3月27日、サイエンスカフェみたかが開かれました(主催 三鷹ネットワーク大学推進機構、企画 くらしとバイオプラザ21)。お話は東京大学名誉教授 長澤寛道さんによる「アメリカザリガニから地球環境へ」でした。アメリカザリガニが脱皮をするときの殻は?主成分の炭酸カルシウムは?と追っていくと、地球上の石灰岩、大気組成、地球温暖化につながるという壮大なお話に、参加者はびっくりの連続を楽しみました。

配信中の長澤寛道先生
自己紹介
福岡県生まれ。東大卒業後、修士課程では花を咲かせるホルモンの研究をし、博士課程から15年間はカイコの脳がつくる脱皮と変態を制御するホルモンの研究を行った。その後、東大海洋研究所(中野区)で「バイオミネラリゼーション」(生物が鉱物をつくる反応)に定年まで関わった。定年後は中国浙江大学でアルテミアの休眠に関するホルモンの研究を行った。専門は微量でも生きるうえで重要な働きをする有機化合物を対象にする「生理活性物質科学」。
アメリカザリガニの脱皮~石灰化と脱石灰化
東大海洋研究所へ異動したときに、海の生物としてクルマエビを研究対象にした。それまで使っていたカイコは家畜化されていて桑の葉さえ与えれば容易に飼育できたが、クルマエビは海水や餌が必要で、餌で海水が汚れると長く生きられず飼育が難しかった。そこで淡水で容易に飼育できるアメリカザリガニを併用した。アメリカザリガニは水が少なくても少しは生きていられるので輸送も簡単。こうして、クルマエビとアメリカザリガニの脱皮・変態に関わるホルモンの研究を始めた。そのうちに昆虫と甲殻類の大きな違いを探りたくなった。甲殻類の殻はとても堅い!そうだ、殻に注目した研究をしよう!
アメリカザリガニ
アメリカザリガニは節足動物門 甲殻綱(昆虫はここが昆虫綱となる)に分類され、アメリカ南部を起源とし、食用に養殖されている。寄生虫が多く加熱調理しなくては食べられない。中国のザリガニ産業は2兆円余りで、本当にこんなに食べられているのかと思ってしまう。食用蛙の餌として、1930年にアメリカから輸入されたのは、途中で死んだりしてたったの20尾。沖縄と北海道以外の全国に広がった。イネに害を及ぼすので2023年に、特定外来生物に指定された。
アメリカザリガニの殻(外骨格)の構造を見ると、4つの層(上皮細胞の薄い層、外クチクラ、内クチクラ、メンブレン層)からなり、内・外クチクラ層に炭酸カルシウムが含まれている。脱皮が近づくと、古いクチクラ層の炭酸カルシウムが溶け出し(脱石灰化)、胃で石をつくる(石灰化)。脱皮が終わるとこの胃石を溶かし、周りの水の中のカルシウムや炭酸を取り込んで新しい硬いクチクラ層をつくる。さらに、ザリガニは抜け殻を食べて、炭酸カルシウムとして再利用する。胃石は脱皮する間、炭酸カルシウムの貯蔵庫になる。このように一個体中で石灰化と脱石灰化が同時に起きる!
4-5尾ずつアメリカザリガニを水槽で飼っていたら、ある朝、1匹足りなくなって、胃石が2個、水槽に残っていた。夜の間に共食いし、硬い胃石だけが消化されずに残ったのだ。12-3cmのザリガニだと脱皮直前には胃石は直径8-10㎜にもなる。

アコヤガイ、胃石、耳石の実物
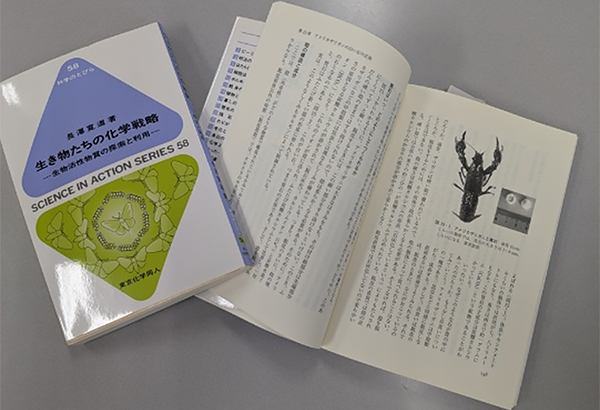
ご著書「生き物たちの化学戦略」
甲殻類と昆虫類の脱皮のちがい
甲殻類と昆虫類の脱皮ホルモンは同じ化合物でステロイドとよばれる化合物群に属する。
昆虫では脳ホルモンがアラタ体から分泌され、その刺激を受けて前胸腺で脱皮ホルモンが合成される。甲殻類では、飛び出した眼のところにあるX器官で合成される脱皮抑制ホルモンがサイナス腺から分泌され、Y器官で脱皮ホルモンの合成を抑制しているが、その抑制がなくなると脱皮ホルモンが合成される。
アメリカザリガニの胃石について
アメリカザリガニの胃の前方に1対の胃石板という組織がある。脱皮間期(脱皮と脱皮の間)には、胃石はない。脱皮前期になると胃石が胃石板とクチクラ層の間につくられ、胃のかなりの部分を占めるほど胃石が大きくなる。脱皮が終わると急速に溶かされて2-3日でなくなり、新しいクチクラ層に取り込まれ、硬い殻を形成する。
胃石は炭酸カルシウムだけでなく有機物も含んでいる。胃石を酸で処理して脱灰するとキチンとタンパク質でできたふわふわした不溶物が残る。このふわふわのタンパク質の主成分はGAMP。GAMPは分子量5万で505のアミノ酸からなり、キチンにも炭酸カルシウムにも結合する。GAMPをつくる遺伝子は胃石板のみで発現する。GAMPの免疫染色を行うことで、胃石板の上皮細胞でつくられ、胃石の中に入っていくことが観察できた。
炭酸カルシウムは炭酸イオンとカルシムの組み合わせで3種類の結晶をつくる。どの結晶も直方体(カルサイト、アラゴナイト、パテライトの順に安定)だが、アモルファスといって、結晶にならないのもある。
例えば、アコヤガイの真珠や魚類の耳石はアゴラナイト。アメリカザリガニの胃石はアモルファス。生物が積極的に関わって結晶の種類を決めている。アモルファスの炭酸カルシウム(非晶質)は溶けやすく、あえてこの形をとって脱皮の時に素早く溶かせるようにしている。
ザリガニ以外の生物の石灰化
いろいろな生物が鉱物をつくる。単細胞の藻類、アコヤガイ、魚の耳石、鱗(リン酸カルシウム)、サンゴ(炭酸カルシウム)。
円石藻の持つ炭酸カルシウムでできたココリス(円石と呼ばれ、円石藻の表面につくられる炭酸カルシウムの構造物)の形態から藻類の種を知ることができる。
アコヤガイはカルサイト結晶、アラゴナイトが真珠の輝きを生じさせているが、真珠のできかたには未知の部分が残されている。
耳石は輪状に一層ずつ毎日大きくなっていくので、植物でいえば年輪のよう。耳石は溶けないので、生育環境を推測する道具に使われる。例えば、海と川を回遊するサカナではストロンチウムが多い海水では耳石にストロンチウムが取り込まれる。ウナギの耳石のストロンチウムが多い部分は海にいた期間を示している。耳石のストロンチウムの解析によって一生を海で過ごすウナギも存在することがわかった。
バイオミネラリゼーション
不溶性の有機物(キチン、コラーゲン、セルロース)が土台になって、バイオミネラリゼーションが起こる。バイオミネラリゼーションは日本でできた和製英語で真珠の研究者が唱えたことば。生物にとっては、体を形作る、防御する、平衡感覚の維持などの働きがある。
6億年前に殻をもった生物が誕生した。原始の地球では、大気の97%が二酸化炭素だった(今は0.045%)。石灰化のお蔭で地球の88%の炭素が石灰化生物の遺体でできた石灰岩になって、長い年月のうちに大気中の二酸化炭素を激減させた。
地球上の生物による二酸化炭素の固定は、「光合成」と「石灰化生物」によって行われている。石灰化によって、地球の全炭素の88%が固定され石灰岩になっている。
地球上の炭素の分布をみると、大気中の炭素は600億トンだが、石灰岩にはその10万倍、堆積物中の有機物には1万倍の炭素が固定されている。従って、二酸化炭素の減少に石灰化生物の貢献は極めて大きい。
太陽系の惑星のうち火星、金星と地球の大気組成を比べてみると、地球だけがとびぬけて二酸化炭素が非常に少なく、酸素が多い。これは、光合成生物と石灰化生物による。
「生物」がいて初めて現在のような地球環境をつくられてきたといえるのではないか!
地球温暖化による石灰化生物の危機
地球の温暖化により、氷山が解けたり、海面が上昇したりしている。その原因のひとつは二酸化炭素濃度の上昇。人間活動で発生した二酸化炭素のうち、森林、海洋に吸収されなかった41億トンが地球温暖化に影響を与えている。さらに温暖化で海水温が上昇して、海洋の石灰化生物であるサンゴとそこに共生する生物が死ぬ。海水の酸性化が進むと石灰化が阻害され、石灰化生物の成長が阻害される。
バイオミネラリゼーションは地球環境と強く結びついている。魚類の耳石やウロコ、真珠、ヒトの骨、歯、腎結石もバイオミネラリゼーションによるものであり、我々の実生活にも結びつきが深い。
石灰岩は古代文明の形成に貢献
石灰岩は比較的軟らかいため細工がしやすく、ピラミッド、コロセウム、マヤ遺跡、パルテノン神殿など古代社会において重要な建造物の材料に広く利用されてきた(日本の城の石垣は火成岩が多い)。
まとめ
アメリカザリガニの石灰化と脱石灰化のメカニズムに始まり、様々な生物の石灰化の共通性が明らかになってきたが、そのような石灰化生物の石灰化反応が長い間に地球の大気組成を変化させるまでになった。しかし、現在人間活動による大量の二酸化炭素の排出は地球温暖化と海洋の酸性化を引き起こし、石灰化生物の生育を脅かしている。
