植物育種イノベーションにおける科学政策に関する意見交換会開かれる
植物育種イノベーションにおける科学政策に関する意見交換会(主催 アメリカ台湾協会、アメリカ大豆輸出協会、クロップライフアジア)を行うために、台湾政府関係者や研究者など12名の代表団が3月10日に来日しました。代表団はゲノム編集生物の環境影響評価と食品としての安全性、ゲノム編集食品をめぐる規制、リスクコミュニケーション、メディアとの関係などについて日本やアメリカの関係者からヒヤリングを行い、13日にはゲノム編集GABA高蓄積トマトが開発された筑波大学を訪ねました。くらしとバイオプラザ21は3月12日の意見交換会に参加したので、当日の話題提供の内容について報告します。代表団の事前調査で、くらしとバイオプラザ21が400回を超えるサイエンスカフェを行い、日本でも最もサイエンスコミュニケーションを行っている団体であるということがわかりヒヤリング先に選定されたそうです。

佐々義子

小島正美さん
話題提供1
「バイオテクノロジーを用いて作られた食品を巡るコミュニケーション」
くらしとバイオプラザ21 佐々義子
くらしとバイオプラザ21からは「バイオテクノロジーを用いて作られた食品を巡るコミュニケーション」として、遺伝子組換え食品が30年前に日本に輸入され始めてから今まで、消費者の受け止め方、その間に行われたリスクコミュニケーションについて報告しました。さらに、大阪学院大学 田中豊教授との共同研究として、心理モデルを用いた因子分析について説明しました。私たちは心理モデルをもとにしたアンケートをリスクコミュニケーションの折に実施し、自らのリスクコミュニケーションの評価を行っています。最後に、最重要事項は食料の安定供給であり、そのために使われる技術(遺伝子組換え技術やゲノム編集技術を含む育種技術、病虫害を減らすための農薬、安全に長期間保存するための食品添加物や冷蔵・冷凍技術など)が適切に理解されるように活動していきたいと述べました。
参加者からは、「日本の消費者はゲノム編集や遺伝子組換えを使った農林水産物の環境影響を気にするか」「バイオテクノロジーを嫌う人に出会ったらどうするか」「遺伝子組換えもゲノム編集も先端バイオ技術であるのになぜ日本ではゲノム編集食品は受容されているのか」「政府はどのようにしたら信頼を得られると思うか」「対象ごとにリスクコミュニケーションの方法を変えるか」などの質問がありました。
話題提供2
「ゲノム編集食品~市場流通が実現するためには何が必要か」
ジャーナリスト 小島正美さん
初めは遺伝子組換えに批判的な記事を書いていたが、アメリカやスペインの現場を視察する機会を得て、農家の規模に拘わらず生産現場では収量・収益が増えていることを知り、認識が変わった。それからは、誤った報道には訂正要望を出すなどファクトチェックの活動も始めた。2013年に毎日新聞の記事に対して旧モンサント社が訂正要望を出し、私も同様に訂正を求めたところ、訂正と謝罪記事が出た。謝罪を伴う訂正記事はめったに出ないので驚いたことを覚えている。その後、大手新聞ではセンセーショナルな記事は激減したように思う。この例のようにファクトチェックは有効だと思う。取材を受けたら、長く良い記事を書いてもらえるようにその記者を育てる気持ちで接してほしい。またバイオテクノロジーに理解をもつ仲間作りも大事。例えばゲノム編集超多収米を栽培したいという鳥取県の大規模農家の徳本修一さんを取材、紹介するうちに、今では徳本さん自身が有名になって露出が増えている。これも仲間作りの成果だ。
今の状況をみると、遺伝子組換え作物・食品は受け入れて輸入されているが、国内栽培だけができていない。その理由は、
- 反対運動があって、日本の試験栽培や開発が止まってしまった
- 2000年に未承認コーン「スターリンク」が混入する事件があり、メディアで大騒ぎになり、イメージが悪化した。
- 自治体による栽培規制で実質的に国内栽培ができなくなった。
- 自国産の遺伝子組換え種子がなくて、外資巨大企業の種子に頼るしかなかった。
- 2009年に政権交代が起こり、日本発の組換えイネ試験栽培が白紙になった。
- 「組み換えでない」という任意表示によって消費者にネガティブなイメージが広がった。
- 風評被害を理由に地元での栽培の同意を得るのが難しかった。
- メディアでは市民団体に寄り添った報道が続いた。
- 農水省が国産でない遺伝子組換え作物の導入に積極的でなかった。
消費者の半分はネガティブイメージを持っているが、日本には遺伝子組換え作物が大量に輸入され流通している。扱っている人は安全だと理解している。ことに食用油メーカーは大きいメリットを知っていて安い油糧作物が大量に輸入されている。スマホはよくない点があると言われる中で、便利で圧倒的なメリットがあるから伸びてきたのと似ている。理解する消費者を増やすより、魅力ある商品を提供するほうが大事。
日本ではゲノム編集マダイ、トマトが上市されているが、消団連のアンケートだと組換えもゲノム編集も半分はネガティブ。しかし、国のルール策定が迅速に進み、モノが出てきて現場できちんと開発者が説明をすると批判的な論調は減っていったと思われる。スシローの経営者も会見で、すしネタとしてゲノム編集魚を広げようと言っている。NHKは上市前からずっとゲノム編集には肯定的。サナテックシードの竹下社長が自信たっぷりに説明したら、記者は納得したようだった。一般の消費者4000人に苗を配って栽培体験をしてもらったのも効果的だった。開発者が研究開発棟に記者を案内して情熱的に語ったこともプラスに働いた。消費者にしっかりと説明できる流通事業者の理解も重要。トマトのケースをまとめると、生産者メリット、消費者メリット、流通が扱うメリットがあった。
ゲノム編集魚は学者中心のベンチャー企業「リージョナルフィッシュ」が開発した。学者が記者に熱く語ると、記者は悪く書けない。「日本の水産業を救うため」という大きな目的を掲げて開発を始め、自社の利益のためではないという印象を与えた点はとてもよかった。自治体がゲノム編集フグをふるさと納税返礼品に採用したことや、同社がイノベーションコンテストで多数の受賞を獲得したことも、前進の原動力となった。反対運動にひるまないリーダーがいることも重要だ。今後は、養殖施設をもっと記者に公開して、良い記事を発信してもらうことが必要だと思う。
まとめると、
- 皆が食べて支えている様子を情報発信し、ゲノム編集はノーベル賞を受賞した技術であることを繰り返し言うことが重要。
- 日本の研究者のベンチャーが日本の農林水産業を救うためにゲノム編集食品を開発し、これまでの遺伝子組換えと異なり、ゲノム編集では農林水産省が後押しした点はプラスに働いたと言える。
- 記者はアクションに引っ張られる。反対運動にせよ、開発ベンチャーにせよ、メディアの目に留まるアクションが必要だ。
- 消費者は商品に魅力があれば、不安があっても買いに行くことを頭に入れておく。
参加者からは、「反対派の人たちとは今はどういう関係か」「アメリカの現場に取材に行くようになったきっかけは何か」「日本のメディアはゲノム編集に肯定的か」「小島さんは詳細に取材されていると思った」などの質問や意見が寄せられました。
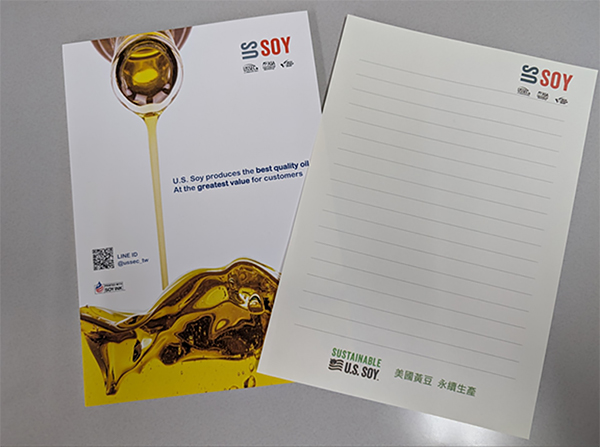
ダイズのインクを使ったメモ用紙

懇親会ではゲノム編集トマトのお料理
