コンシューマーズカフェ「誰もができるSDGs~私にできる“フードロス削減”を考える」
2025年1月15日、オンラインコンシューマーズカフェを開きました。お話は消費者庁消費者教育推進課食品ロス削減推進室長 田中誠さんによる「「誰もができるSDGs~私にできる“フードロス削減”を考える」でした。消費者、研究者、企業、メディア、いろいろな立場からの参加があり、具体的な情報提供から、それぞれが自分のこととして考えることができました。
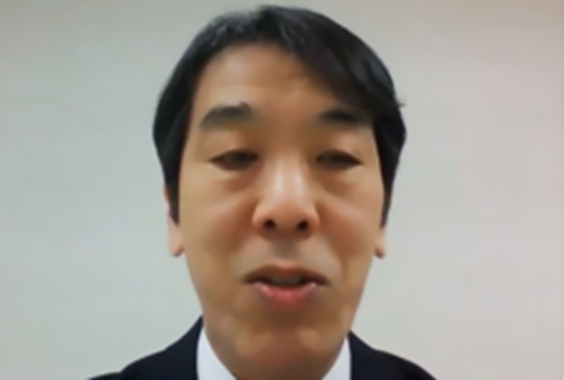
田中誠 室長
お話の概要
食品ロスの発生状況
令和4年の食品廃棄物のうち、まだ食べられるものが食品ロスで、それは472万トン。食品ロスとは食べられるものなので、エネルギーを使ってリサイクルするより、まずはちゃんと食べましょう! その内訳は、規格外のものや3分の1ルールに外れたものが含まれる「事業系」と、食べ残しや直接廃棄などの「家庭系」で半々。
「3分の1ルール」とは、製造日から賞味期限までの3分の1を過ぎた商品は納品できない、3分の2を過ぎたら販売できないという商慣習。
472万トンとは、1年にひとりあたり38kg、毎日おにぎり一つ分の食べ物を捨てている計算になる。日本は3200万トンもの食料を輸入しているのにも関わらず、約10分の1以上捨てられていることになる。
事業系食品ロス(236万トン)の内訳をみると、製造段階で発生する食品ロス117万トンはパッケージ印字ミスや返品等により廃棄されたりする。外食から出る食品ロスは60万トンでその半分は作り過ぎや客が食べきれずに食べ残している。事業系の食品ロスの発生原因は多様。
家庭系食品ロス(236万トン)の内訳をみると、主に食べ残しと直接廃棄。直接廃棄は手つかずのまま捨てられるケースで、調査によれば、きゅうり、もやし、豆腐、納豆、食パンが上位を占める。食べ残しと直接廃棄の他は、ブロッコリーの軸や根菜類の皮の厚向きなどの「過剰除去」。
472万トンの食品ロス量を基に「経済損失」を推計してみると約4兆円。人口ひとりあたりにすると、1日に88円で、おにぎり一つ分と大体合っている。温室効果ガス排出量として推計してみると、1,046万t-CO2となるが、これは国民1人あたり食品ロス8%削減すると、エアコンで冷房温度の設定を1度上げるのに相当する。
4兆円の推計方法は農林水産省からの事業系食品ロスと環境省からの家庭系食品ロスのデータを生鮮食品(19部門)と加工食品(29部門)に振り分けて、産業連関表をもとに価値に置き換えて再構成した。その合計が4兆円。環境負荷についても「産業連関表による環境負荷原単位データブック(3EID)」に基づいて算出している。
2015年、国連「持続可能な開発サミット」で採択されたSDGsの17のゴールの12番目「つくる責任、つかう責任」は食品ロス削減と関連している。世界の人々のために生産される食料の3分の1にあたる13億トンが世界規模で捨てられている。日本でも9人の子どもうちの1人が生活困窮者。生活困窮者に食べられる食品を配れないか。
食品ロス半減に向けて
日本では、2015年のSDGsをうけて令和元年10月1日に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行され、翌年には食品ロスの基本方針が閣議決定された。2000年を食本ロス元年として家庭・事業系食品ロスを2030年までにそれぞれ半減して、両者を合わせて489万トンにする。その基本方針は5年ごとに見直すことになっていて現在は令和7年度からの次の基本方針に向けてパブリックコメントを募集した。
消費者がすべきことは、買い物前の在庫チェックの徹底、外食での適正な注文など、当然のことだがとても重要。企業では3分の1ルールを2分の1ルールにして納品期限を長くしたり、容器包装の工夫で賞味期限を延長したりするなどが考えられる。国や地方公共団体は普及啓発活動、食品関連事業者の支援や未利用食品の循環。たとえば、恵方巻は予約発売による需要に応じた生産やAIを活用することで作りすぎないようにする、値引き販売で売り切る、外食の食べ残し防止のための小盛りメニューや持ち帰り推進などが行われている。次の基本方針ではこのようにより具体的に記述していく。
事業系食品ロスはすでに半減目標を達成しているが、コロナ禍で外食営業が縮小したことに連動して削減されたことも考えられる。また、インバウンドも活性化しているなどからリバウンドが起きるのではないか、との懸念がある。
コロナ禍前の直近5年の平均をみると、家庭系が280万トン、事業系が334万トンで合わせて614万トン。2030年までの目標はそれぞれを216万トン、273万トンとなり、あと約100万トン以上の削減が必要である。
殊に、事業系食品ロスでは、外食段階の食べ残しのうち20万トン(調理加工食品)の持ち帰り、食品製造業と食品卸業のうちの24万トン(食べられるのに返品)と家庭系食品ロスでは直接廃棄のうちの「賞味期限表示をみて全く手つかずのまま廃棄」の14万トンを食品寄付に回すことで、さらに食品ロス削減ができるのではないか。
農林水産省が把握している食品寄附の活動を行うフードバンクは279団体(令和6年11月15日時点)ある。しかしながら、事業者には寄附した食品がきちんと管理されて食中毒が起きないか、横流しにつながらないかという不安がある。信頼できるフードバンクに出会えないリスク、フードバンクへの輸送コストを考えると、廃棄したほうが良いという結論に行きつく。
そこで、2030年度までに達成する半減目標にむけた多様な取り組みを消費者庁、農水省、環境省、こども家庭庁、法務省、文科省、厚労省、経産省で横断的に「施策パッケージ」として取りまとめた。中でも食品寄付の促進のために国のガイドラインに従っているフードバンクを定める、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(2024年12月25日とりまとめ)」に基づく安全な持ち帰り、廃棄物の発生抑制(3分の1ルールの見直しも含まれる)、賞味期限の意味の浸透は消費者との関りが大きい。
食品の期限表示について
劣化の早い食品(弁当、そう菜)には、過ぎたら食べないほうがいい「消費期限」が使われ、劣化が遅い食品には、おいしく食べられる目安である「賞味期限」が用いられる。劣化の遅い食品では、試験結果に基づいて設定された期限までを1として、それに0.8をかけたものが賞味期限とされている。これをできるだけ1に近い適切な安全係数にできたら、賞味期限切れで廃棄される食品を減らせるかもしれない。
そもそも、食品期限表示は平成17年に通知されたガイドラインによって設定されている。ガイドラインでは生鮮食品から加工食品も対象になっている。食品期限表示には、理化学試験、微生物試験において数値化できる指標に基づいて設定すること、設定された期限に1未満の「安全係数」をかけた期限より短い期間に設定するのが基本などのルールがある。
令和6(2024)年5月から検討会が始まり、令和6年度末をめどに食品ロス削減、食品の安全性確保、などの観点から食品の期限表示の見直しが検討されている。ぜひ、注目してください。
食品寄附ガイドライン
施策パッケージに基づき、それぞれが食品寄附に関わる責任を果たせるために守るべきガイドライン策定について、官民協議会で議論された。
ガイドラインの対象は、食品寄附者、中間支援組織(フードバンク等)、直接支援組織(フードパントリー、こども食堂)、受益者すべて。これらの関係者は、たとえボランティア団体であっても食品衛生法、食品表示法に従わなければならない。
ガイドラインには、転売の禁止、食品の品質・衛生管理、食品表示情報の伝達と管理、事故時の対応(保険の加入)、財務管理では損金算入ができる、などが記載されている。
食べ残し持ち帰り促進ガイドライン
食べ残しの持ち帰りによって食中毒が起きた場合の責任はだれにあるのか。事業者には法的責任関係の整理が必要だった。事業者・消費者が安心して食べ残しの持ち帰りを促進できるように、事業者、消費者が求めていたことが整理された。
注意事項を守って、消費者は自己責任のもと、持ち帰った食品を食べきる、「契約」ととらえる。事業者は注意喚起をしなければならない。消費者は持ち帰る際及び持ち帰った後の食品の管理の責任は基本的に消費者にあることを理解しなくてはならない。さらに食べ残し持ち帰りサービスを提供する飲食店の取組を消費者も評価しサポートしていくことが望ましい。
第2次「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(案)」
2022年度の食品ロスは家庭系も事業系も236万トンずつで、家庭系はまだ20万トン届いていないが、事業系はすでに目標達成できていることになる。そこで事業系についてさらなる数値目標を設けた。方針は「教育・学習振興、普及啓発」、「食品事業者の取組への支援」、「実態調査や調査・研究」、「未利用食品の活用、食品寄附活動の支援」が中心になっている。
食品寄附の推進は福祉政策でもあり、とても重要。食品ロス削減、食品寄附促進、食品アクセスの確保を省庁横断的な取り組み「食の環」プロジェクトと位置付けて進めていく。
ぜひ、参加者の皆さんは、パブリックコメントにも意見を寄せ、これからも注目してください。
質疑応答
- 年月表示のメリットは何か。
「逆転のルール」というのがある。例えば1月15日の賞味期限のものを納品した後に1月14日のものが倉庫から出てきても、逆転になるので納品できない。これが年月表示だと解消できるなどのメリットがある。一方で、賞味期限の日付でロット管理している場合、問題が発生した際に月管理だと1か月分回収することになるので、やりたくないという事業者もいる。 - 安全係数0.8の決め方は?
実態を調査すると、0.5、0.7、0.8などがあったが、0.8くらいが多かったので、ガイドラインとしては0.8とした。安全係数は伸ばしてほしいと考えるので、他部局とも連携して検討していく。 - 3分の1を過ぎたものを、寄附ではなく安く買い取るというやり方はないのか
海外ではフードバンクが安く買い取るところがあるが、日本のフードバンクの財政基盤は脆弱で買い取る財力があるところが少ない。安く買い取るビジネスをするスタートアップが出始めている。 - 賞味期限の設定について、夏と冬では劣化の度合いが違うので、安全係数を大きくしてよいか、悩ましいところがある。消費者庁ともご一緒に相談させてもらいたいと思っている。
- 企業の立場から大くくり化についていえば、賞味期限8月31日の製品は月表示だと7月末になってしまうこともあり悩ましい。大くくり化と賞味期限延長はバランスを取りながら検討していきたい。
悩みながら生まれてきた良い取り組みは会社の宣伝に使ってください。大臣表彰もしています。 - ボランティア活動をしていると、古着は多いがフードバンクへの寄附は本当に少なく、食品寄附は浸透していないと思う。
- 海外の食品ロスの状況や、食品寄附の様子を教えてください。
特に家庭系の食品ロスの実態の調査はとても手がかかり、海外ではあまり行われていない。アメリカのフードバンクには企業や銀行が出資していて、フードバンクの基盤がしっかりしている。フランスには食べられるものを捨ててはいけないという法律がある。韓国もロスにならないように国や企業が寄附に回すようにする。海外の食品寄附は日本よりも規模が大きく、国、企業や銀行が積極的でその背景には税制優遇などの仕組みがある。 - コロナ明けで外食産業のリバウンドが心配。
令和5年のコロナのリバウンドとインバウンドの回復は理解している。リバウンドを吸収できるくらい良い政策、仕組みづくりに取り組もうと、野心的な目標を立てて頑張っているところ。事業者は本来、無駄を出したくないので本当にロス削減は進んだ。家庭系で、安くて複数パックで売られているような食品の廃棄を減らせる手立ては特に悩ましい。 - 家庭の立場では、安くても捨てるときには罪悪感がある。学校教育が大事だと思う。
10代の子どもたちは学校で食育、食品ロス、SDGsなどの言葉に小さいころから触れているので、意識が高くなっていくと期待する。
