サイエンスカフェみたか「加工食品の安全はどうやって調べるの?―食品微生物検査の大切さについて」
2024年11月28日、サイエンスカフェみたかをオンラインで開催しました(主催 三鷹ネットワーク大学)。お話は エルメックス技術顧問(元新潟食料農業大学教授)丸山純一さんによる「加工食品の安全はどうやって調べるの?―食品微生物検査の大切さについて」でした。2024年は紅麹を使った機能性表示食品の健康被害から、食品の安全性評価への関心が高まった年でした。そもそも食品の安全性はどうやって調べるのか、食中毒を中心に食品の安全性の調べ方について具体的にお話しいただきました。
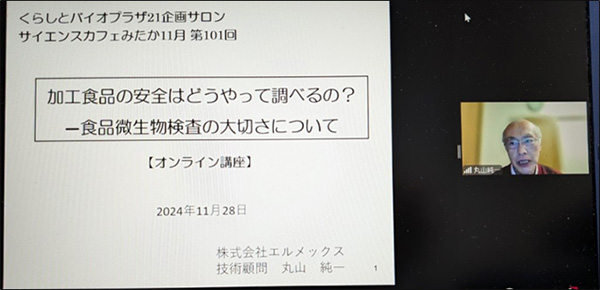
オンライン講座

顕微鏡で観察(エルメックス㏋より)
主な内容
「食べる」とは化学物質をとりこんで体内で分解し体を形作る化学反応のこと。CODEXは食品安全の国際機関で、食品の定義をしている。そこでは、「予期された食べ方や意図された方法で作ったり食べたりした場合、その食品が害を与えないこと」、これが「食品の安全」と言っている。
1.食中毒の概要
食中毒は原因で分類される。微生物、自然毒、化学物質、アレルギー、寄生虫の5つがある。発⽣件数および患者数は年次により⼤きく変動する。保健所に届けられたものだけが食中毒と認識され、届け出られないものは入らないので実際はもっと多いだろう。
主な病因をみると、減ってはいるがノロウイルスが1位。カンピロバクターは微増。寄生虫アニサキスによる食中毒は件数と患者数が同程度(1件あたりの患者数が少ない)。食中毒の8-9割が微生物原因。だから微生物管理が大事!!
2.原因物質
〇ノロウイルス
ヒトの腸管内だけで発育。感染力が強く、ウイルス10-100個でうつる。実際には人の糞便や吐しゃ物から人に感染する。不顕性感染者の糞便にもウイルスが出ている。
感染者による調理、患者の糞便や吐しゃ物などの処理(これが多そう)、下水からウイルスの流れてくる海に棲む二枚貝(あさりは一日にバケツ2杯ぐらい水をとりこむ)が感染源となっている。なぜカキで多く発生しているのかというと、ウイルスが貝類の内臓にたまるためで、ホタテなどのように内臓を除去するケース、シジミやあさりのように生食しない(加熱して食べる)ケースは食中毒になりにくい(広島などカキの生産県では行政の指導で厳しい品質管理が行われており、生食用と表示されているカキは生食可)。このように食中毒の起こる原因やどうして起こりやすいのかの理解が重要。
予防は手洗い、殺菌(加熱調理、次亜塩素酸ナトリウム)。手洗いは流水とハンドソープで100万個から数個まで除菌できる。その証拠に、コロナ中は手洗い徹底でノロウイルス被害が減少したが、今は増えてきた。
〇カンピロバクター
鶏肉、豚肉、牛肉の保菌率が高い。少量で発症する。
カンピロバクターは75℃1分で死滅する。食品中では酸素濃度3~15%の嫌気的な環境を好み、空気中では元気がなくなる。鶏肉を水洗いするのはカンピロバクターが飛散して他の食材についたりするので危険、鶏肉のぬめりは清潔なクッキングペーパーでふき取る。
流しそうめんで800人がカンピロバクターの食中毒を起こしたことがある。山などの湧き水は鳥や動物の糞などで汚染されていることがあるから安全とは言えない。
湧き水の消毒は少量ならば煮沸消毒、大量に使用する場合には次亜塩素酸ナトリウムを添加するのがよい。
〇病原性大腸菌 O157
大腸菌がたまたまベロ毒素をつくるプラスミドをもらって病原性を持つようになったもの。小腸粘膜細胞に感染して毒素を分泌する。感染後に毒素を出す。
O157とは(O抗原とH抗原の組み合わせでいろんな型がある)、大腸菌の中のひとつの腸管出血性大腸菌O157のことをさす。
動物の腸管内におり、牛の腸の常在菌でもあるので、と殺時に肉の表面に付着することがある。O157は少量でも食中毒を発症する。菌は75℃1分で死ぬ。自家製たい肥で栽培したきゅうりでO157食中毒が起こったこともある。
〇黄色ブドウ球菌
人の皮膚の傷やふけにいる菌。祭りなどで提供されるおむすび、穀物に、調理した人の菌がついて、食中毒が起こることがよくある。黄色ブドウ球菌は、食品中で熱に強いエンテロトキシンを産生する。加熱して菌は死んでも毒素が残る。「殺菌後、菌をつけない、増やさない」ことが重要。10℃以下ならエンテロトキシンを産生できなくなる。
24年前の雪印食中毒事件の原因は製品の製造中に停電事故が起こり、増殖した菌により産生されたエンテロトキシンが製造再開後の加熱処理でも残ったためだった。吉田屋の弁当、伊勢定のうなぎ弁当など、大量に調理した時の手洗い不足が原因だろうと考えられている。
〇ウェルシュ菌
ウェルシュ菌は、土中、水中、生物の腸などにいる。酸素がない環境を好む。耐熱性の芽胞を菌体内につくる。食品を加熱してウェルシュ菌は死んでも芽胞が生き残り、ゆっくり冷やされると、酸素がない状態で発芽・増殖する。
シチュー、カレー、煮物などの大量調理の時、深い鍋で嫌気的になったときに起こりやすい。調理後は急速冷却して芽胞を発芽させないこと、冷蔵保存した食品を再加熱して食べるときには、良くかき混ぜながらしっかりと加熱することが大事。
〇肉類の生食
肉類では、牛肉の生食には厳しい規格基準があったり、生レバーの生食が禁じられたりしている。豚肉は生食提供禁止。肝炎、寄生虫など厳しい健康被害が現れる。鶏肉のカンピロバクター食中毒では、激しい症状(ギランバレー症候群)が出ることがあるので、生食は絶対に避ける。
ジビエには指針がある。食肉の加熱殺菌には基準あり、63℃30分と同等の殺菌効果を得るには55℃5時間の加熱が必要。低温加熱がいいと思っている人がいるが、1℃違うと殺菌効果が大きく変わる。自宅での低温調理は要注意!
〇まとめ
食中毒は、1885年からの死者数の調査によると1960年から明らかな減少を見せている。衛生状態の改善、行政指導、普及啓発活動による意識改革のためだと考えられる。
- 腸炎ビブリオは海水が20℃以上のときに出現し、好塩性(真水は生育しない)。低温では発育しないので、10℃以下で温度管理ができるようになり、成分規格基準が設定され(ゆでたこでは1グラム当たり100個以下でなくてはならない)、加工基準や保存基準が設定されたお蔭で今は食中毒が減った。
- サルモネラによる食中毒も、「卵製品の製造・加工・調理段階における規制」(厚労省 平成11年)ができて、加工・調理基準ができ、食鳥卵の規格基準ができ、表示基準ができて、食中毒は減少した。生産段階でも輸入ひなの検疫、鶏卵サルモネラ総合対策指針策定など管理が行き届くようになった。
3.食品微生物検査
(1)検査の目的
食品衛生法第6条で、「健康を損なう恐れのある食品の製造・加工・販売」が禁止されている。出荷していいかどうかを判定するために検査を行う。そのもとになる規制は食品衛生法、衛生規範、自治体の指導基準など。たとえば、加熱せずに食べることのできる惣菜は一般細菌10万個以下でなければならないなどのルールがある。
消費期限は、生肉など5日以内に消費しないといけないもの。それより長いものは賞味期限とする。評価項目は理化学試験、微生物試験、官能評価。0.7~0.8の安全係数を掛けて消費期限・賞味期限を決める。
(2)検査の種類
- 培養検査法(人工培地で細菌を発育させる)
- 迅速簡便法(自動機器、検査キットを使う)
- 遺伝子検査(病原体の遺伝子から、病原体が何かを調べる)
- 生物的検査(培養細胞を使ったウイルス検査)
(3)検査方法
公定法(行政が定める)、検査指針などに示された方法、簡易迅速法(公定法と同等とみなされているキットなどを使う)、独自の検査法(特殊な食品はメーカーで検査法開発)
(4)検査項目
汚染指標菌(一般生菌数、大腸菌、カビ・酵母)、食中毒原因菌、乳酸菌、ビフィズス菌などを調べる。検査項目によって検査方法が決められているが、基本的に培地を用いた培養法による。例えば、一般生菌数は標準寒天培地など、培養する菌によって培地が異なっている。
(5)培養法
サンプリングして希釈して培地に接種して培養。生えてきた細菌のコロニーをカウントして判定する。
ひとつの食品の5か所以上からはさみとピンセットで10~25gをサンプリングすることが決まっている。
お弁当などでは、まとめてみるか、特定の具材を検査するかも決めて行う。
試料の全部をミキサーし、10~25gをサンプリングするには殺菌したミキサーが検体の数だけ(場合によっては数百台)必要になる。ディスポの容器に10~25gサンプルを入れて粉砕する機器(ホモジナイザー)を用いれば多数のサンプルの検査ができる。10~25gのサンプリングでは少ないのでは?と思うかも知れないが、熟練者が検査すれば安定した結果が出る。
最終的には、一般細菌が10万個以下、大腸菌群、黄色ブドウ球菌は基準より少ないことがわかったので合格!(生食用惣菜の場合)となる。
(6)今後の課題
食中毒の過半数が飲食店で起こっている。今はすべての食品事業者にHACCPに沿った食品衛生管理の実施が義務づけられている。
企業や組織では、食品安全文化を経営トップから全従業員までがしっかり深耕していかなくてはならない。
質疑応答
- 馬刺しは生食だが、大丈夫だろうか。
馬刺しは処理場が決まっていて衛生的な処理が行なわれたものだけが生食用になっている。 - 嫌気性の菌が増えるものとして芋煮はどうか
芋煮は深い鍋でつくるものではないので該当しないだろう。
