
 |
輸入食品検疫・検査センター見学記 |
 |
|
2008年7月24日(木)、食のリスクコミュニケーション円卓会議により、輸入食品・検疫検査センター(神奈川県横浜市金沢区長浜)の見学会が開かれました。
はじめに滝本浩司センター長から検査の種類、検疫所の役割などのお話をうかがい、センター内を見学し、意見交換会を行いました。検査の目的は混入などの事故を見つけることでなく、モニタリングをいつも行っていることにより、関係者の安全への意識を高めることだと繰り返し言われたセンター長のお話が印象的でした。
横浜検疫所 http://www.yokohama-keneki.go.jp/
はじめに
検疫所は厚生労働省の施設等機関のひとつで、全国には13の検疫所本所があり、輸入食品・検疫検査センターは神戸と横浜の2箇所があり、検査項目ごとに分担しています。
検疫所には1)検疫法に基づく検疫・衛生業務、2)食品衛生法に基づく輸入食品の監視・指導業務、3)感染症法に基づく動物の輸入届出審査の業務があります。
当輸入食品・検疫検査センターは平成7年に長浜に開設され、全国の約28%の検査を担当しています。検査の内容は、検疫法に基づく検査と食品衛生法に基づく検査を行っています。
横浜検疫所は、明治12年、コレラに対応するための法律が箱崎にできたのが始まり。
明治28年に長浜に移転し、長浜検疫所となりました。野口英世がここで明治32年、ペスト患者を発見、隔離するという成果を上げたことは有名です。
 |
 |
| 輸入食品検疫検査センター入り口 |
滝本浩司センター長 |
検疫所の役割
検疫所には大きく分けて5つの業務があります。
検疫衛生業務:ヒトの感染症の侵入・蔓延の防止のために、来航する船舶・航空機の検疫や輸入動物の管理を行う。
輸入食品監視業務:食品衛生法に基づき、輸入食品等の安全性を水際で確保するために輸入食品監視・指導業務と輸入食品相談指導を行っている。輸入食品監視・指導業務では、次のような検査を行っている。
命令検査:食品衛生法違反の蓋然性が高いと判断される食品などについて厚生労働大臣が輸入者に対して命ずる検査で登録検査機関が行う。(費用は輸入者が負担する)
行政検査:初めて輸入する食品や食品衛生法で違反があった食品の確認、輸送途中で事故が発生した食品の確認のために行う検査で登録検査機関が行う。(費用は輸入者が負担する)
モニタリング検査:食品衛生法違反の蓋然性が低い食品などについて、年間計画に基づいて検疫所で行う検査
試験検査業務
・理化学検査:輸入食品中の残留有害物質(バナナ、アボガド、マツタケなどの農薬)、残留動物医薬品(マグロなど)、加工食品中の添加物、カビ毒などをガスクロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィーなどで分析する。一斉分析法では百数十項目を一度の分析で行う。
・微生物検査:輸入食品、海外渡航者、感染症を媒介する蚊やネズミを対象に、コレラ菌、マラリアの原虫などの病原体を検査する
・遺伝子組換え食品:ダイズ、パパイヤ、トウモロコシ、米等について、未承認の遺伝子組換え食品の混入の確認や承認済遺伝子組換えダイズやトウモロコシの含有率を定量的に検査しIPハンドリング(分別生産流通管理)が適正に行われているどうかの確認を行っている。
信頼性確保業務
検査の信頼性確保のために手順書や記録などの定期的な検証、管理資料を用いた試験などを行い内部精度を管理、第三者機関による試験を通じて外部精度管理を行う
輸入食品監視支援業務
輸入食品監視支援システム(FAINS)を用いて食品等の輸入手続、届出情報の統計解析を行っている。
横浜検査センターの働き
モニタリング検査は年間計画に従って実施され、延べ件数は79,665件(平成18年度)。
横浜検査センターに届く検体は、少ないときで100件/日、多いときは200件/日。11時頃までに受け付けて試料を調製し検査する。農薬のポジティブリストが定められてから検査項目も増えました。
残留基準のない農薬等については一律基準0.01ppm(0.01ppmとは東京から下関の道程における1cmに該当)を用いるが、これはかなり厳しい基準値である。
検査項目が増え、検査内容が多様化すると、高度な装置が導入され、メンテナンスなど、職員の負荷は増加。40人の職員で行っている延べ検査数は2万〜4万件。試験品採取には2人一組で出向く。検査した検体は3ヶ月、検査データは3年保管する。
  |
見学 |
検体の受付
試験品は、宅急便などで搬入され、受け付けられるとそれぞれの検査方法に従って試験が行われます。
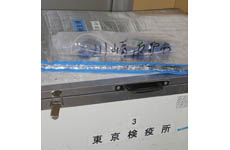 |
 |
検体には温度計をつけて搬入し、途中の
温度変化で変質していないかをチェックする |
検体の受付手続き |
残留農薬の検査
穀類は粉砕し、野菜は定められた部位(地下部だけをすりつぶす野菜、葉と茎をすりつぶす野菜など)をペースト状にして試料を調製し、残留農薬などを調べます。
 |
 |
| 穀類は粉砕する |
野菜はペースト状にし、検査項目を示す書類と一緒にする |
 |
 |
| 必要な部位を切り出す器具は厨房と同じ |
すりつぶす容器が沢山並んでいる |
 |
 |
| 試料を暖めながら回転させて揮発分を取り出す |
検査項目を指示する用紙 |
 |
|
| 指示された項目の検査を行う |
|
微生物検査
微生物検査の部署には衛生動物室、実験動物室(P3)、細菌検査室、食品検査室などがあり、窓の外から見学しました。
 |
|
| 微生物検査室の見取り図 |
|
放射線照射食品
日本ではジャガイモの芽止め防止以外での食品照射は禁止されています。ここでは、平成19年7月6日の厚生労働省医薬食品局安全部監視安全課輸入食品安全対策室長から各検疫所長への通知により、香辛料に放射線が照射されているかどうかを熱ルミネッセンス測定法で調べています。この方法では、食品に付着している微量の砂埃のような鉱物質を採取し、70度から490度まで加熱したとき、鉱物中に蓄えられた放射線エネルギーが光の形で放出される発光量を測定します。たまたま食品に付着した鉱物の量はまちまちなので、これだけではどれだけの放射線を受けていたかは分かりません。そこで、その試料に一定量の放射線を原子燃料工業株式会社熊取事業所(大阪)で照射した後、もう一度加熱して発光量を測定します。このとき照射した線量と、その後の温度上昇と発光量の関係を示すカーブと最初の温度上昇と発光量のカーブとの違いから、それ以前に受けた放射線の線量がある程度推定でき、その食品が照射されていたかどうかが推定できます。
参考サイト:http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/hassyutu/dl/326.pdf
 |
 |
| 大きな袋に入ったハーブ(調製前) |
調製した試料はこぼれないように工夫
された容器に入れて大阪に送られる |
 |
|
| 試料はこの台に載せて測定する |
|
検疫資料館
海岸を埋め立てる前の長浜検疫所は海を臨み風光明媚な地として有名で、現在は資料館になっています。ここで、与謝野晶子、高浜虚子らは吟行会を開いたそうです。
 |
 |
| 燻蒸消毒中の船に掲げられた「立ち入り禁止の旗」 |
昔のマスク、防護服が展示されている |
 |
 |
| 美術品のような洗面器 |
隔離された船員が使っていた蚊帳 |
  |
意見交換会 |
|
は参加者、→はスピーカーの発言 |
検疫所の皆さんと参加者で、話し合いを行いました。主な内容は次の通りです。
モニタリング検査について
- モニタリング検査は違反の可能性の低いものの検査の意味を説明してほしい。怪しいものをモニタリングで見つけるとはどういう意味か→輸入された食品等が、食品衛生法に違反する可能性が低い食品等について、その食品の衛生状態を把握する調査を目的で行う検査が、モニタリング検査です。この検査の方法は貨物の流通を認めながら検疫所で行う検査であり、検査結果が出るのを待たずに届書を返却します。しかし、検査結果が、食品衛生法に適合しなかった場合は、その食品等は回収、積み戻し、廃棄等の措置が指導されます。
- 残留農薬や食品添加物は100倍の安全係数がかかっているので、たとえ違反していても、すぐに健康被害が起こることはないが、継続して検査する。流通をとめるほどの違反の蓋然性が低いものをモニタリングすることになる。例えば、アフラトキシンやO157が1回見つかれば、直ちに流通をとめる。
- モニタリング検査では検査しつつ流通させていくと聞いたが、それでは全量保管はできないのではないか→日持ちがしないものは検査結果を待たずに流通違反がわかると回収になるので、日持ちするものは業者が検査結果を持って待っていることがある。最大1週間で結果を出している。
検査品目に関すること
- 組換えのアルファルファ、テンサイ、ナタネが対象になっていないのはなぜか→承認済み作物を定量的に検査(5%以内の非意図的混入か、適正表示か)するので、対象はトウモロコシとダイズということになる。通知よりナタネは検査項目に入っていない。
- コーヒーはリスクが高いのか→コーヒーの残留農薬で検査命令の対象になっている。エチオピアのコーヒーの中に農薬で問題になったものがあり、市場ではモカが少なくなっていると聞く。急に違反が増えたのではなく、コーヒーの協会からのポジティブリストのデータ提出が遅かったために、1年目は問題にならなかったが、2年目から項目が増えて問題になってしまっている。
- 牛肉で特定危険部位が見つかったときはどんな検査をするのか→農林水産省は家畜伝染病予防法により生きた家畜を検査し、ここはヒトの健康の観点から検査する。BSEはヒトと牛の両方に関係している病気。手続き上は家畜伝染病予防法が優先法となる。植物の場合は植物防疫法が優先法となる。
センターの役割
- 福田首相が冷凍ギョーザ事件後、こちらを視察されたそうだが、なんと言われたのか→検査所が横浜と神戸の2箇所しかないのは少しは心配。消費者目線で監視を続けてほしいということで、スタッフが一生懸命やっていることは理解してくださったようだ。
- 食品衛生監視員は、公務員削減の中では珍しく、増加している。来年度にむけた体制の強化を図りたい。
- センターの役割で大事なことは何ですか→食の安全の責任を誰が持っているのかを理解してもらうべきだと思う。例えば、食品メーカー、輸入業者の責任を認識してもらいたい。餃子の残留農薬検査を我々は行ったが、輸入業者が自分達で原材料の選択、製造過程の自主管理を促すことになると思う。効率的に全体の底上げができるような検査を実施したい。中小業者だけでなく大手でも事故が起こることはある。食品業界が消費者目線で、健康を守る姿勢をしっかり示してもらいたい。市民からもそういう発信をしてもらいたい。それぞれのメーカーがコンプライアンスを持つ、業界の結束を高める、消費者からの監視の目の中で自主管理をしている企業が生き残るようになるのがといいと思っている。
その他
- 別な検体を検査するときに、残留農薬の容器を洗うにはどんな洗剤を使うのか→検査用の洗剤を使う。ネガティブコントロールを入れて異物混入の確認のラインを並行して行っている。
 |
|
| 説明して下さった皆さん |
|
|