
 |
一般向けバイオテクノロジー実験講座(都立科学技術高校)が開かれました |
 |
|
2006年11月18日(土)〜19日(日)東京都立科学技術高等学校において同校、茨城大学遺伝子実験施設、日本科学未来館友の会とNPO法人くらしとバイオプラザ21の共催で、標記実験講座を開きました。高校生から年配の方まで15名が参加しました。
はじめに、同校の鳥居雄司校長先生より開会で次のようなご挨拶がありました。
「本校は、2001年4月に東京都教育委員会が新しくたてた科学技術科に属する第1校目の高校として「理系」「進学」をキーワードに開校した。独自の教科書をつくり、独自の教育活動を実施している。今回のように幅広い団体の連携の活動を行えることは喜ばしいことで、これを機に、今後も継続していきたい。」
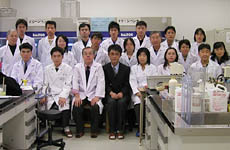 |
 |
| 全員写真 |
鳥居校長のお話 |
  |
主なスケジュール |
第1日
講義1 「バイオテクノロジーとは?」 茨城大学遺伝子実験施設 安西弘行先生
実験1 「DNAをはさみで切る」
実験2 「納豆菌・大腸菌の培養」
実験3 「光る大腸菌をつくる」
第2日
講義2 「食虫植物の大量培養について」 東京都立科学技術高校 佐藤浩史先生
実験4 「DNAを見る」(電気泳動と染色)
実験5 「納豆菌のDNAを取り出す」
まとめ1 「光る大腸菌の観察とまとめ」
まとめ2 「電気泳動の結果のまとめ」
(すべての実験指導は安西先生によって行われました)
茨城大学遺伝子実験施設 安西弘行先生
(詳細は茨城大学遺伝子実験施設で開催報告のホームページを参照)
 |
 |
| 安西先生の講義 |
お話をされる佐藤先生 |
都立科学技術高等学校 第3分野バイオ化学系 教諭 佐藤浩史
絶滅危惧種の保護
私は準絶滅危惧種の保護について、同僚と一緒に考えるようになったのがきっかけです。絶滅危惧の原因としては、開発で水辺の環境が失われ、自生地が非常に限られてきたこと、更に、このような植物を人間がたのしみで採取してしまうこと、森林の手入れが行き届かないことなどが挙げられる。
絶滅危惧種には以下のような段階がある。
絶滅(EX):日本ではすでに絶滅したと考えられる種
野生絶滅(EW):飼育・栽培下でのみ存続している種
絶滅危惧=絶滅の恐れがある種
絶滅危惧I種≪CR+EN≫ 絶滅の危機に瀕している種
絶滅危惧 IA類(CR) ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種
10年後50%以上絶滅する
絶滅危惧 IB(EN) IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種
20年後20%以上絶滅する
絶滅危惧 II(VU) 絶滅の危険が増大している種
100年後10%以上絶滅する
準絶滅危惧(BT) 現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種
情報不足(CD) 評価するだけの情報が不足している種
参考サイト: http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_top.html
食虫植物とは
葉などで虫や小動物をつかまえて消化し、栄養源とする植物で、世界には11科20属560種ある。代表的なものの1つとして、モウセンゴケがある。
モウセンゴケの葉の表面には、紅紫色の腺毛が密生しており、粘性のある分泌液を出して、小動物を捕らえ、溶かす。アフリカナガバモウセンゴケはチーズのかけらを葉にのせると、巻き込んで溶かしてしまう。食虫植物は一般的に、根からの栄養吸収はあまりしない。寒天培地上で育てる栄養量も従来の植物より少なくてよい(MS培地の半分の栄養に3%蔗糖、0.8%寒天)。私は、モウセンゴケを主に、培地の組成を変化させより良く育つ研究をしている。
モウセンゴケの大量培養
モウセンゴケは日当たりのよい湿地に生える食虫植物。寒天培地上で、器官培養によって増殖した苗を更に大量に増やしている(20−25oC、300ルクスの光を16時間/日あてて栽培)。 春先には土壌に植えて育て、楽しむ。
マヨネーズビンに入れたモウセンゴケの苗を希望者の方に配布します。培養ビンのまま春まで育ててください。その後、ビニール袋をかけて日陰におき、水を切らさないようにしながら、日のあたる場所に移動してください。
 |
 |
| マヨネーズ瓶に入ったモウセンゴケ |
寒天培地には活性炭が入っている |
マルバモウセンゴケには白い小さい花が、ナガバアフリカモウセンゴケには紫の花が咲くが、これらモウセンゴケはワシントン条約の対象となっており、大切にされている植物である。
モウセンゴケを選んだ理由
食虫植物の大量培養は本校の専攻科の授業、高校3年の本科の中で、器官培養法を学ぶところで扱っている。私自身はコチョウランやエビネランの培養も行っている。
生態系の循環
生態系には、生産者→消費者→分解者→生産者・・・・・・という連鎖、循環がある。循環する系を学んで、環境保全(植物保護)について考えていただきたい。
  |
実験講座の様子については、写真で示します。 |
 |
 |
| 安全ピペットを使っての実験 |
寒天培地上に生育した大腸菌を拾い上げる |
 |
 |
| 光る大腸菌ができた |
寒天ゲルへのDNA注入説明 |
 |
 |
| 電気泳動後のDNAバンド |
大腸菌でお絵かき |
  |
出席者からのアンケートの中から、遺伝子組換え技術について、今回の実験講座を通じてどのように感じられたかを聞いてみましたところ以下のとおりでした。 |
(1)変化
| 認識が大きく変わった | 4人 |
| 認識が多少変わった | 4人 |
| 新しい知識は得られたが認識そのものは変わらない | 4人 |
| 特に変わらない | 2人 |
| 未回答 | 0人 |
(2)内容
| これまで感じてきたほど危険でないと思った | 6人 |
| これまで感じてきたよりも危険だと思った | 0人 |
| これまで思っていたよりも有用なことがわかった | 4人 |
| これまで思っていたよりも有用でないことがわかった | 1人 |
| その他 | 2人 |
コメント
- 特に変わらない。特別危険ではないと思っていた。使用法や利用の仕方で危険性の有無は変わると思う。
- 身近なことだと感じた。一般には組換えの理解が進んでいないように思うので、こうした情報がより広報されるとよいと思う。
最新のバイオテクノロジーの講義と実験を行う本講座は、バイオテクノロジーを理解するうえで大切であり、今後も続けていきたい。
|